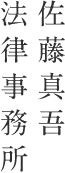長時間労働・過労死・労災
うつ病と労災
長時間労働が原因となって、うつ病になるケースがあります。最悪のケースは、そのうつ病を原因として自ら命を絶つケース(過労自殺)です。当職は、過労自殺案件についての労災請求を代理し、労災認定していただいた経験がありますが、当職が取り扱ったその事件の後、平成23年12月、厚生労働省は、業務上の精神障害の労災認定に関して、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めました。この認定基準は、厚生労働省のウエブサイトで見ることができます。この認定基準では、発病前3か月間連続して1か月あたりおおむね100時間以上の法定外時間外労働を行っていた場合は、業務による心理的負荷が「強」と認められるとされています。また、1か月間の法定外時間外労働時間が80時間を超えると、業務による心理的負荷の強度は「中」とされています。心理的負荷の強度が「中」の場合は、それとは別の心理的負荷の強度が「中」の業務による心理的負荷の出来事があれば、全体的に見て、業務による心理的な負担の強度が「強」とされる場合があるとされています。心理的負荷の強度が「強」とされる場合は、ほかに特段の事情がなければ、うつ病などの認定対象となる精神障害を発病していれば、労災認定がなされます。さて、上記の認定基準をいま少し具体的にイメージしてみましょう。たとえば、完全週休2日制の会社で、始業時刻が午前9時、昼休みが1時間、終業時刻が午後5時であるとすると、午後6時以降の残業が法定外時間外労働時間になります。1か月の労働日が仮に20日だと仮定すると、1日あたりの法定外時間外労働時間が平均5時間になれば1か月間で合計100時間になります。1日に5時間の法定外時間外労働をするということは、午後11時まで残業するということになります。具体的なイメージとしては、平均して午後11時までの残業が3か月も毎日続いているのであれば、うつ病になったとしたら、それは業務が原因であると考えるべきだ、といったところでしょうか。毎日午後10時まで残業した場合だと、上記の例では、1か月の法定外時間外労働時間が80時間になり、心理的負荷の強度は「中」です。このような場合は、労働時間の長さ以外に、業務による心理的負荷が「中」になるそのほかの出来事がいくつか重なれば、うつ病を発症したことは業務が原因とみるべきだ、といったイメージでしょうか。一生懸命仕事をする従業員がうつ病になることは、会社にとっても損失です。経営者の方々においては、個々の従業員の労働時間を定期的にチェックし、恒常的な長時間の残業を発見したならば、それを解消する方策、できるだけ時間を短くする方策を検討すべきです。元気に効率よくしっかり働いてもらうためにこそ、しっかり休んでもらう必要があるのです。
「賃確法」ってご存じですか?
退職した後に未払いになっている給料や残業代などを請求したい、ということで法律相談にお越しになる方もよくいらっしゃいます。その際、ご自分なりに訴状を書いてみて、それをご持参になる方もいらっしゃいます。賃金請求権に関してご本人自身が作成された訴状でよくあるのが、遅延損害金の利率について、年5%と記載されているものです。退職した後に、賃金請求をする場合は、「賃金の支払の確保等に関する法律」(通称「賃確法」)の第6条1項により、遅延損害金の利率は年14.6%とされていますから、この利率に訂正するように助言することがよくあります。この条文は、民法の年5%の利率の特則なのです。仮に、請求額が60万円で、退職してから1年経過していると、1年分の遅延損害金は、年5%で計算すると、3万円にすぎませんが、年14.6%で計算すると、8万7600円です。5万円以上の差があります。遅延損害金だからといって軽視できないのです。ちなみに、民事訴訟には「処分権主義」という原則(当事者が請求していないことは判断しない、という原則)がありますし、裁判官は中立の立場です。ですから、訴状の請求の趣旨に「年5%」と書いてあるとすると、裁判官から、本人訴訟であることを踏まえて、「数字の記載なども含めて訴状に誤記はないですね?」くらいまではおっしゃってもらえるかも知れませんが、それ以上の指摘をしていただくことは無理な望みというものです。本人訴訟で裁判を起こす場合でも、訴え提起前に、弁護士からアドバイスを受けたうえで申し立てた方が、得策だと思います。
「労災保険に入っていない」ことはできません。
勤務先で業務作業中に業務が原因で大けがをしたのに、使用者が「労災保険に入っていない」というので、労災申請できないと思った、という従業員の話を、法律相談で耳にすることが、今でも、まれにあります。使用者も従業員も、両方とも、労災保険が、強制加入保険であることを、知らないのです。労災保険法が明文で定めるごく僅かな例外の場合を除き、使用者が法人であれ個人であれ、従業員が正社員であれパートであれ、一人でも雇用契約をしたならば、労災保険関係は成立するのです。ですから、使用者が、手続きのために労基署に提出する書面のタイトルは、保険関係成立「届」なのです。労基署からの何らかの応答の意思表示を求める「申込書」とか「申請書」ではなくて、「届」なのです。要するに、雇用によってすでに法律上成立した労災保険関係を、使用者が、労基署に「届け出て」いるのです。労基署で手続きをとらないと労災保険関係が成立しない、というのは、全くの誤解なのです。ちなみに、私は、労災保険は、労災から、従業員を守るのであると同時に、使用者を守るものであると思います。というのも、従業員が労災で亡くなったり重篤な後遺障害を負った場合に、使用者において、安全配慮義務違反が全くなく、完全に無過失であることのほうが、むしろ、可能性として少ないと考えられるからです。そして、労災保険で給付された金額によって、本来使用者が賠償すべき損害の一部を填補できるのです。使用者が、労災保険の加入手続きをとっていないと、労基署から、未払い労災保険料を徴収されるだけでなく、労災保険給付額の全部または一部が「費用徴収」されることになるのです。平成17年11月から、費用徴収を強化する運用がなされていますが、労災保険制度のフリーライドを禁圧する観点からは、全くもっともな運用だと思います。労災保険料は、額自体、微額の経費です。このような、事業運営に当然に必要で、しかも、微額の経費を削ってまで、万一の場合に「費用徴収」を受けるリスクを負うことは、事の是非の問題以前に、そもそも経済的な損得勘定において大きな損であるように思うのです。
ハイスピード審理への対応~労働審判の準備について
労働審判という手続きをご存じでしょうか。使用者と労働者間の労働関係に関する紛争解決のための手続きです。労働審判手続の最大の特徴は、「スピード」感のある手続きだということです。労働審判手続は、原則として3回の期日で迅速に審理されます(労働審判法第15条2項)。また、第1回目の期日は、原則として申立てから40日以内に開かれます(労働審判規則13条)。しかも、労働審判手続きでは、第1回目の期日から、いきなり争点について立ち入った内容のやりとりが行われます。手続きに入ってから争点を明確にするのではなく、そもそも「予想される争点」を申立書に記載し、それに関する証拠もはじめから明示していくこととなっており(同規則9条)、いきなり最初から争点について実質的な審理ができるような手続きになっているのです。いうまでもなく、その審理の準備のためには、時間が必要です。私は、労働審判の手続において代理人として関与した経験がありますが、労働審判の審理手続では、審判官から尋ねられたことには基本的に即答できるように事前準備が必要です。全部で3回しか期日がなく、2回目の期日の最後に裁判所(労働審判委員会)から調停案を提示(同規則22条)されて次回までに検討してくるようご指示をいただくことも多く、3回目の期日は、調停での結論を出せるかどうかの期日であって、実質的な審理のための期日ではないことも多いのです。労働審判手続では、このようなハイスピード審理が怒濤のように展開されるので、当事者であれば答えることが可能だと思われるような事柄についての質問に関しては、「持ち帰って確認の上、次回期日でお答えします。」というような回答では全然要領を得ないのです。私は、申立人の側で代理人として関与したので、準備時間についてそれほど大変な思いをしませんでしたが、申立てを受けた相手方の代理人の先生の準備は、時間的にタイトで相当大変であったろうことは想像に難くありませんでした。労働審判を申し立て「られた」なら、すぐにその対応について検討し始めないと、準備時間がほとんどないままに手続きに対応せざるを得なくなります。弁護士に代理人を依頼するにしても、第1回期日までに時間がないと、準備不足のままに手続きに入ることになります。そういうわけで、労働審判を申立て「られた」なら、「すぐに」、弁護士に相談することをおすすめします。
残業代は基本給のなかに入ってますって言われても・・・
従業員から残業代が未払いになっていると主張されて、会社側の方のご相談を受ける場合があります。「基本給の中に残業代も入っているんです。」と主張したいとの相談、よくあるパターンです。たしかに、基本給自体が相場からすると若干高めで、おっしゃりたい意図はよくわかるのですが、このような主張は、裁判所から認められる見通しに乏しい主張です。判例では、割増賃金(残業代)とそれ以外の部分との「明確区分性」がないと、残業代を支払ったとはいえない、とされています。私は、こういう場合、早期の和解をお勧めするとともに、就業規則ないし賃金規則等の整備をすすめるよう、助言しています。ドキッとした人事労務のご担当者もいらっしゃるかと思います。そのままにしておくのは、問題の棚上げにすぎません。信頼できる弁護士などに相談して、紛争の予防を図ることも大切ですよ。
残業代請求について
残業代請求の事件は、労働者側を代理する弁護士にとっては、正直、つらいものがあるのです。なぜかというと、異常なまでに立証の手間がかかるからです。何より、「平成〇年〇月〇日は、午前〇時〇分に出勤し、午後〇時〇〇分に退勤した。」という事実を、1日ごとに、タイムカードやパソコンの記録やタコグラフの記録などを証拠にしながら、特定する作業をするのです。1日ごとに特定しないと休日労働の割増率の違いを計算できませんし、何時の残業かを特定しないと深夜残業の場合の割増率の違いを計算できませんし、このような地道な積算をしないと1か月60時間を超えた部分の割増率をアップさせる計算もできないのです。ただ単に、時間外労働の合計時間を計算すればよいということではないのです。弁護士は、労働時間の特定と割増賃金の計算のために、証拠の厳格なチェックの上、パソコンと一日中にらめっこしながら何日かがかりで表計算ソフトの地道な数値入力作業を余儀なくされるのです。このように、途方もない手間が非常にかかる一方で、賃金債権の時効期間が2年であるために、請求額がさほど大きくならないことが多く、そのために、弁護士報酬が手間に見合うほど大きいとは言えない、というのが正直なところなのです。私は、労働者側の代理人として残業代請求をしたこともあります。私が取り扱った案件は、いずれも、極めて労働時間が長く、しかも、残業代を払わないというケースでした。一番ひどかったケースは、法定外時間外労働が2年以上にわたり恒常的に月100時間を超え、繁忙期には何と月200時間超の法定外時間外労働が数か月続いたという案件でした。過労死する相当の危険が生じる残業ライン(法定外時間外労働が月100時間)を軽く超えており、それが恒常化していたケースでした。そのうえ、働いた分の賃金さえ払わないで済ませようというものでした。 このように、残業代請求は、とても手間のかかる作業なのです。しかし、働いたら賃金が発生し時間帯によっては残業代も発生することは、きわめて基本的なルールです。働いたのに給料を払わないのは、明らかなルール違反です。従業員側からみれば、働いたのに給料が支払われないことは全く納得できないことですし、企業側にとってみても、このような基本的なルールを守ることは、長期的に見て、企業が発展するための、重要な基盤であるとも思うのです。