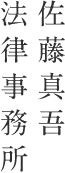新着情報
当事務所では、令和3年12月24日、債務整理・個人再生・過払金 一日無料相談会を実施します。相談枠は8枠です。事前予約制です。ご予約は、0166-39-3180まで。お気軽にどうぞ。
当事務所の佐藤真吾弁護士が、令和3年10月8日、新型コロナワクチンの2回目の接種を終えました。
ある紛争を解決するための手続きとして、民事調停という手続きがあります。簡易裁判所で行う手続きで、調停委員2名と調停主任(裁判官)の3名で調停委員会を構成し、当事者双方から事情を聴いてもらい、双方が合意できるよう双方の主張のすり合わせをし、双方の合意が形成されれば、調停成立にいたります。調停が成立した場合は調停調書が作成されますが、これは、裁判上の和解と同一の効力を有します(民事調停法16条)。和解調書は、確定判決と同一の効力を有します(民事訴訟法267条)から、調停を成立させることで、紛争の解決を図ることができます。
ところで、民事調停の場合、申立てをしても、相手方が調停の席につかず、欠席することも考えられます。この場合、裁判所からの呼び出しに応じないことで、裁判所が過料を科すこともできると定められておりますが、出席を強制できるものでもありません。
こういった事情から、最初から民事訴訟という手続きを選択するようにすることも多いのが現実です。
しかし、民事調停には、民事訴訟手続には代えがたいメリットがあるのです。それは、秘密の保持です。
民事訴訟手続は、憲法で裁判の公開原則が定められていることとの関係で、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」のが、原則とされ(民事訴訟法91条1項)、閲覧ができないのは例外的な場合に限られます。このように、新聞記者や雑誌記者も、民事訴訟手続では、その事件記録は、原則として、閲覧可能なのです。
ところが、民事調停手続では、事件記録の閲覧は、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」が行うことができ、これに該当しないものは、閲覧請求ができないのです(民事調停法12条の6第1項)。すなわち、利害関係がない新聞記者や雑誌記者は、民事調停手続では、その事件記録を閲覧できません。
もしも、あなたが、自分の係争案件だけ解決されればそれでよく、相手方に対して、当該係争案件について、第三者に対して秘密を守る考えがあるなら、そのことを、民事調停の申立書に記載して、民事調停手続での事件解決を目指すことも考えられるのではないでしょうか。相手方が、当該案件での失態を何とかして秘密にしたいと考えているなら、調停成立の可能性も見込まれると思われます。
「全部秘密にするから、私のこの案件だけでいいから、どうか解決してもらえませんか?」このようなアプローチは、民事訴訟手続ではできませんが、民事調停手続であれば可能です。当事者の秘密を保持できる民事調停手続は、活用次第で、事案の早期解決を図ることも可能な手続かと思います。
自然災害は、起きないことにこしたことはないのですが、日本では、最近でも、各地で甚大な被害を伴う自然災害が起きています。東日本大震災をはじめ、この北海道でも、台風による洪水など甚大な災害に見舞われました。自然災害と弁護士とはあまりイメージが結びつかないかもしれませんが、自然災害に遭ったときにも、弁護士がお役に立てることがあります。日本弁護士連合会では、「災害復興支援委員会」を設置し、委員会活動を行っております。被災された直後から、正しい法的知識や何が後々必要な資料になるかなど、知っているか否かで、被害回復がスムーズに行われるか否か、差が出てまいります。自然災害に遭ったときにも、相談の選択肢として、弁護士を覚えていただければ幸いです。
先日、平成27年11月21日に札幌で開かれた、過労死等防止対策推進シンポジウムを見てまいりました。このシンポジウムの主催は、厚生労働省でした。
私は、平成20年ころに、過労自殺案件について、北海道内の労働基準監督署に労災申請し、労災認定してもらった経験があります。その当時は、国が率先して過労死等防止対策を進めてくれるなど、夢のまた夢のような世界でした。このようなシンポジウムを国が主催して行うに至ったことには、隔世の感があります。今では、国が、過労死防止対策の旗を振っているのです。
過労死事案が、誰にとっても不幸な事象であることを、ようやく社会的に認知されるに至ったということかと思います。亡くなった本人自身も無念でしたでしょうし、家族を亡くした遺族の悲しみは計り知れず、熱心に働き自社で経験を積んできた有能な従業員を失うことで会社側も大きな痛手を負い、社会全体から見てもそのような仕事熱心な人材が働けなくなって生産効率の低下をきたすのです。このように、関係者全員に負の影響しか生じないのです。
過労死案件がなくなることを願ってやみません。
司法試験に合格した後は、司法修習生となって、現在進行形で事件処理されている実務の事案を目の当たりにしながら修習し研鑽を積みます。その中でのエピソードです。私が、実務修習するなかで、最も強い違和感を感じたことは、刑事事件において、「贖罪寄付」をすることにより、これが情状の一つとして考慮されて、量刑が軽くなる事情の一つと「なりうる」と言うことでした。当時の私の頭の中は、「これは、要するに、金で量刑を買うということにほかならないのではないか?」という疑問で一杯になりました。「刑事事件を起こして、罪を償うという問題なのにも関わらず、そんなことがなぜ許されるのか?」などと疑問で一杯になったのです。刑事事件の情状に関する文献もそう多くはなく、修習生であった自分なりにも調べるに調べられず、自分の頭で考えても意味がわからなかったので、私は、刑事裁判修習の際、刑事裁判官に質問してみました。そうすると、その裁判官は、「贖罪寄付は、お金を手放す点に意味があるのです。そういう視点で考えてみてください。」とおっしゃいました。私は、それでもピンと来ず、よくわからないでいると、その裁判官から、「例えば、不法な薬物などを違法に売買して、その違法な活動による収益をしっかりため込んだままの状態で、被告人が、反省していますなどと法廷で述べた場合、その反省の弁は信用できますか?」と問われました。私は、それを聞いて、ようやく贖罪寄付の情状上の意味がわかったのでした。金銭を捨てることは善くないので、社会的に意味のある事業に使ってもらうことにしているだけのことなのだと。誰かに金銭を渡すことに意味があるのではなく、金銭を自分の元から手放し、自分のものでなくすることに意味があるのだと。贖罪寄付は、典型的には、違法な活動で手元に不法な収益が残っている場合に、「金銭を手放すことで真に反省していることを示す」手段であるのだと、ようやく理解できたのでした。そして、同時に、贖罪寄付が被告人の反省の証であるものと裁判官が理解できなければ意味がないのだと気づいたのでした。
弁護士は、もちろん、法律について研鑽を積まなければいけないのは言うまでもないのですが、法律だけお勉強していればよいかというと、それだけでは足りないのです。弁護士のお仕事は、①証拠で事実を立証し、②事実を法規に当てはめて権利主張する、というようにざっくり分けて捉えることができます。法改正などに伴う法律のお勉強は、主として②の部分に関する研鑽なのです。弁護士になった以上、②の部分の研鑽は、本来的なお仕事そのものというべきものですから、もう頑張るしかありません。一方で、弁護士は、①の部分の研鑽も積まないといけません。そうでないと、立証できずじまいで終わり、どんなに優秀に法解釈ができても、結局のところ、依頼者の権利の実現に至らない可能性が大きくなっていくのです。弁護士は、法律のお勉強だけでも四苦八苦しているというのに、①の部分のリサーチは、最初は、門外漢であるだけにちょっと大変なのです。
たとえば、労災請求事件において、「故人であるAさんが、平成〇年△月×日時点で、うつ病になっていたこと」を証明する必要がある場合、弁護士は、うつ病の診断基準を学ぶ必要があります。どういう事情や証拠があれば、うつ病になったと言えるのかについて知らなければ、立証活動は事実上できません。WHOのICD-10やアメリカ精神医学会発行のDSM-5などの基準をしっかり勉強するのでなければ、たとえ専門家である精神科の先生のお話を伺っても、弁護士は、素人なりの理解すらできないのです。これでは立証はままなりません。
また、刑事事件において、「被告人はアルコールと併用した向精神薬の影響で、行為当時、事理弁識能力や行動制御能力がなかったか、少なくとも、大幅に制限されていたのではないか?」という疑いがあり、被告人の責任能力について争おうとするならば、スイス人の精神医学者であるハンス・ビンダー博士が1935年に明らかにした「酩酊分類」の基準を知らずしては、意味のある争いをすることはできないのです。
一般に言われる弁護士の「専門性」とは、①の部分について医学、建築学などをはじめとした専門的な知見を必要とする案件を取り扱うことができること、を意味するのだと思います。弁護士は、もともと司法試験の勉強から始まり法律知識は研鑽して②の部分の専門性を有していますが、最初から①の部分の「専門性」を有している人はまれです。弁護士の「専門性」は、①の部分である立証活動について、依頼者の権利実現のために、徹底的にリサーチすることを通じて、弁護士活動の結果として獲得されるものだと思います。弁護士活動で重要なのは、「①の部分である立証活動について、依頼者の権利実現のために、徹底的にリサーチする執念深さ」なのではないかと思うのです。「情熱」と言えばかっこいいですが、実際には地味で泥臭いものです。「執念」のほうがぴったりくる感じがします。弁護士の「専門性」とは、その弁護士の立証活動にかける「執念」の果実なのではないでしょうか。
佐藤真吾弁護士が担当した裁判例が判例地方自治NO.385(平成26年10月号)、45頁で紹介されました。
佐藤真吾弁護士が担当した裁判例が、季刊労働法246号(2014年秋)190頁に掲載され、解説されました。
他人と話をし、その他人に対して、自分の言い分を聞いてもらおうとする場合、誰でも自分の言い分の理由を伝えるものです。自分の言い分の理由を相手に伝える場合、どのような伝え方をするのか、という問題があります。相手を言い負かす方法である「論破」もあれば、相手にしぶしぶながらも自分の言い分を理解してもらい受け入れてもらう方法である「説得」もあります。テレビドラマなどで弁護士が登場する場合、その弁護士は、反対当事者やその代理人に対して、「論破」する形で、自らの言い分を主張することが多いように思います。それはおそらく、その方が、話の内容として面白いからだと思います。
しかし、実際の弁護士は、そうではありません。 といいますのも、「論破」の方法では、当事者間に、事後に、さらなる対立を生み出す可能性があるのです。ある問題ではやり込められたけれども、ほかの問題で実質的に報復する、ということにもなりかねないのです。これでは、実質的には、「紛争を解決する」という大切な目的を果たしていないのです。これに対して、「説得」は未来志向の解決をもたらす余地を残す手法なのです。「紛争を終結させる」という未来志向の観点からは、「論破」よりも「説得」のほうが優れているのです。
紛争当事者には、感情的になり、ひたすら相手を「論破」してやり込めることを弁護士に期待する方もいらっしゃいます。私は、そのような方には、上記の趣旨のお話をさせていただきます。ご自分の言い分がいかに法的に正当であったとしても、反対当事者には、高等裁判所へ控訴する権利と、最高裁判所へ上告する権利とが、手続を受ける権利として保障されているのです。「論破」の方法では、北風と太陽の関係を煽り立てるだけであり、早期の紛争解決は望めません。「紛争の早期解決」という観点からは、「論破」よりも「説得」のほうが優れた手法なのです。「説得」は、「論破」に比べれば、一見、弱腰な感じに見え、テレビドラマ的には受けが悪いのでしょうけれども、「紛争の早期解決」という大きなメリットを依頼者にもたらしうる手法なのです。「論破」は、「説得」の方策が尽きた場合の、最終手段であると思うのです。